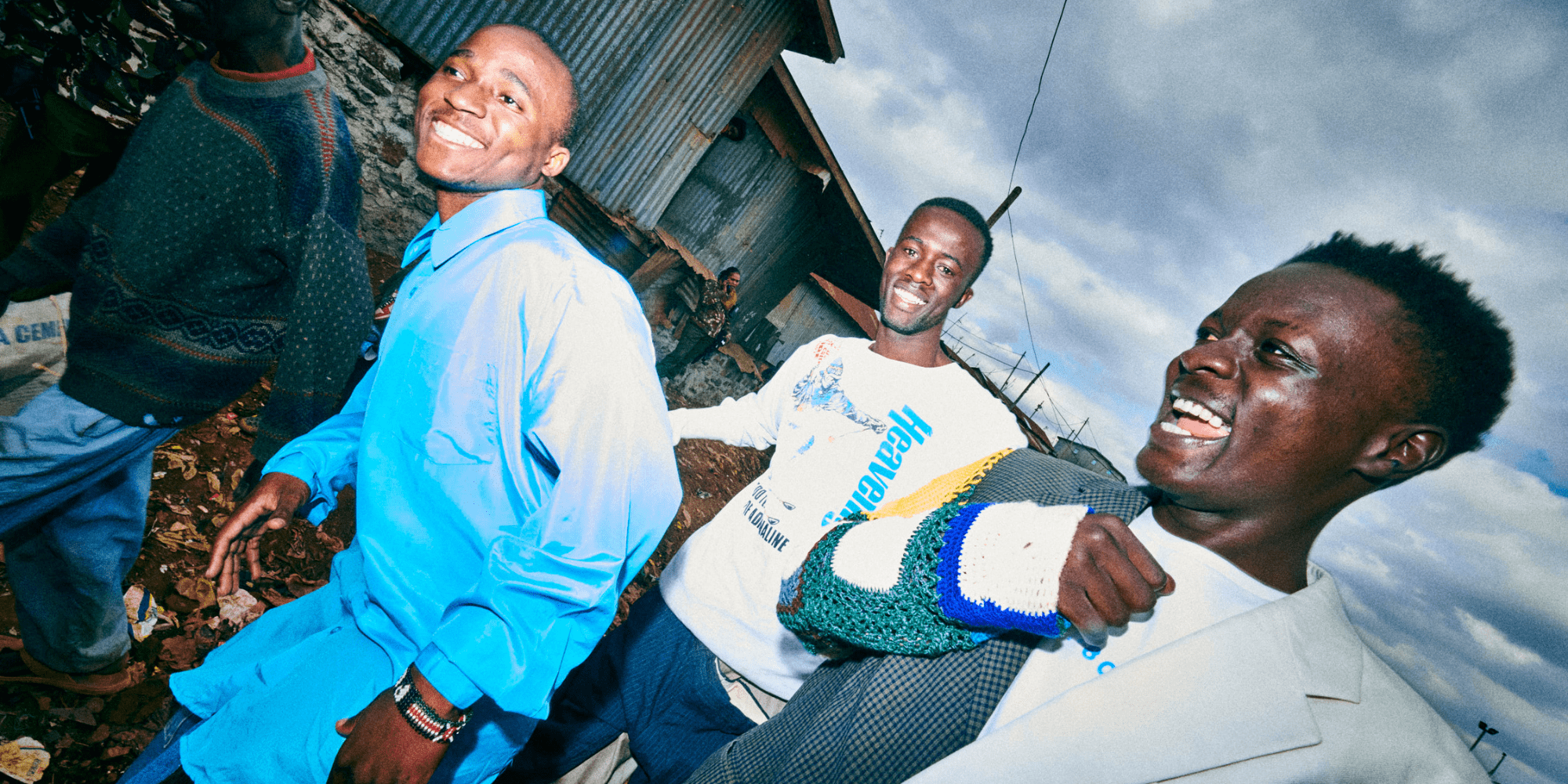1. 本ポリシーの目的
本ポリシーは、NPO法人シフトエイティ(以下「当法人」)が活動するすべての場において、子どもおよび若者の安全と尊厳を守るために定めるものです。当法人は、支援対象となる人々のうち、特に年齢や社会的立場において弱い立場に置かれる者に対して、差別・暴力・搾取・虐待・ネグレクトなど、あらゆる形態の有害な行為からの保護を最優先事項と捉え、組織としての責任を果たします。
本ポリシーは、当法人が行う教育支援、給食支援、医療・衛生支援、就労支援、表現機会の提供、寄付者との交流事業など、すべての活動および関係者に同様に適用されます。
本ポリシーにおける「子ども」とは18歳未満の者を、「若者」とは18歳以上20歳以下の者を指し、当法人ではこの両者をセーフガーディング対象として位置づけます。これは、当法人の活動地における教育・就労・社会的自立の過程が年齢にとらわれない現実に基づいています。
当法人は、全ての関係者が本ポリシーの目的を理解し、倫理的な行動規範に則って行動することを求めます。本ポリシーに違反する行為が発覚した場合、厳格な措置を講じるとともに、被害に遭った当事者の声を尊重し、その安全と回復を最優先に対応します。
2. 本ポリシーの適用範囲
本ポリシーは、以下に定める関係者に適用されます。ただし、実施可能な範囲で、各関係者に理解と同意を求めるものとします。関係者は、業務時間内外を問わず、当法人の活動に関わるあらゆる場面において本ポリシーを遵守しなければなりません。
(1)当法人の役職員・スタッフ
- 正職員・契約職員・アルバイト・非常勤スタッフなど、当法人との雇用または契約関係にある者(雇用形態を問わない)。
(2)ボランティア・インターン・外部協力者
- 当法人の活動に関わるボランティア、インターン、短期・長期協力者、アドバイザー等。
(3)業務委託先・協働パートナー機関
- 当法人と契約関係にある外部団体、提携組織、およびそれらに所属する個人(役職員・ボランティア含む)。ただし、当該機関が独自のセーフガーディング方針を持ち、それを遵守することに合意している場合は例外とする。
(4)取材・視察・交流を目的に活動地を訪れる個人または団体
- 寄付者、報道関係者、研究者、芸術家、著名人、行政関係者など、当法人の許可により受益者と接触することがあるすべての第三者。
本ポリシーに該当する関係者は、当法人の活動に関与する前に、本ポリシーを読み、理解し、同意することを義務とします。また、未成年や若年層と接する機会のある関係者に対しては、必要に応じてセーフガーディングに関する研修または事前説明を行います。
3. 用語の定義
本ポリシーにおいて使用する主要な用語の定義は以下のとおりとします。
(1)子ども
18歳未満のすべての者を指します(国際連合「子どもの権利条約」に準拠)。
(2)若者
18歳以上25歳以下の者を指します。当法人では、子どもと同様に社会的・経済的に脆弱な立場に置かれやすいこの年齢層を特に保護対象とします。
(3)受益者
当法人の支援事業により、直接的または間接的に利益を受けるすべての個人、家庭、コミュニティ、または関連組織を指します。
(4)関係者
本ポリシーの第2項に定める、当法人のスタッフ、ボランティア、業務委託先、視察者など、当法人の活動に関与し、子ども・若者と接触する可能性のあるすべての者を指します。
(5)セーフガーディング(safeguarding)
子どもおよび若者を、あらゆる形態の虐待(身体的、心理的、性的)、搾取、放置、不当な差別、搾取的関係、権力の濫用、またはその他の有害な行為から守るすべての取り組みを指します。
4. セーフガーディングにおける基本原則
当法人は、すべての子どもおよび若者が、安全かつ尊厳をもって生きる権利を有していることを認識し、以下の原則に基づき、活動を行います。
4-1. 子どもおよび若者の最善の利益を最優先とする
当法人のすべての意思決定と行動において、子どもおよび若者の最善の利益が最優先されます。
4-2. 差別のない支援
性別、年齢、民族、宗教、出自、障がい、性的指向、性自認、言語、政治的またはその他の意見等にかかわらず、いかなる差別もなく子ども・若者に接し、支援を提供します。
4-3. 搾取・虐待・暴力・不適切な関係の禁止
関係者は、いかなる形であれ、子ども・若者に対して身体的、精神的、性的な暴力や搾取を行ってはならず、またそれを黙認してはなりません。
4-4. 権力の濫用の防止
支援提供者としての立場や、信頼、権限を利用し、子どもや若者に不利益を与えたり、依存関係をつくるような行為は固く禁じられます。
4-5. 同意とプライバシーの尊重
子ども・若者の写真・映像・ストーリーなどを記録・使用する場合には、必ず本人および、その保護責任者(保護者など)の事前同意を得るものとし、プライバシーおよび尊厳を損なわないよう細心の注意を払います。
4-6. 実効性ある対応体制
すべての関係者は、子ども・若者に対する搾取や虐待が疑われる事象を知った場合、速やかに所定の報告ルートに従い対応する義務を負います。子ども・若者の安全を守るために、当法人は通報が適切に扱われるような仕組みを整えています。
5. 本ポリシーの適用対象者
本ポリシーは、当法人の活動に関わる以下のすべての個人に適用されます。適用対象者は、業務時間の有無にかかわらず、また子ども・若者との接触が直接的・間接的のいずれであっても、本ポリシーに則って行動する責任を負います。
(1)当法人の役職員
- 正職員、契約職員、業務委託、インターン、アルバイトを含む、雇用形態を問わず当法人と契約関係にあるすべてのスタッフ。
(2)ボランティア・プロボノ・実習生
- イベントやプロジェクトに参加する個人を含み、無償・有償を問いません。
(3)公式なパートナー団体およびその関係者
- 現地NGO、行政、教育機関、企業、その他SHIFT80と協定・契約・覚書等を交わし、事業実施に関わる団体およびその職員・関係者。
(4)広報・取材などで関わる外部関係者
- 取材者、メディア関係者、ジャーナリスト、カメラマン、研究者、ドキュメンタリー制作者など、活動地を訪れ、子ども・若者と接する可能性のある外部関係者。
(5)支援者・訪問者
- 支援者、法人会員、寄付者、連携先企業、視察・訪問を行う個人など、当法人の紹介により活動現場を訪れる可能性のあるすべての方。
※ これらの対象者を本ポリシーにおいて「関係者」と総称します。関係者はすべて、本ポリシーを遵守し、違反があった場合は当法人が定める措置を受けることに同意するものとします。
6. 行動規範と禁止事項
本章では、当法人の関係者が遵守すべき行動規範および禁止事項について定めます。これらは、子どもおよび若者の安全と尊厳を守るために必要不可欠な基準です。
(1)尊重と敬意をもった接し方
子ども・若者を一人の人格を持った存在として尊重し、上下関係やステレオタイプに基づいた扱いをしないこと。意思を確認し、発言の機会を与えること。
(2)禁止される行為
関係者は、以下の行為を行ってはなりません。
- 身体的虐待(例:殴る、叩く、つねる、突き飛ばす等)
- 心理的虐待(例:脅迫、怒鳴る、威圧、無視、人格を否定する発言等)
- 性的搾取・虐待(例:性的接触、性的言動、性的関係の示唆、ポルノの提供等)
- 経済的搾取(例:金銭・物品的利益を得る行為)
- 差別的言動(例:出自、宗教、ジェンダー、障がい、人種などに基づく発言)
- プライバシーの侵害(例:同意なく個人情報・画像・映像等を取得・公開する行為)
- 個人的な贈与・金銭の授受(例:本人との間で個別にプレゼントや支援を行うこと)
- 不適切な接触(例:1対1の長時間接触、過度な身体接触)
- オンラインでの無許可の接触(例:SNSやメッセージアプリ等による私的な連絡)
(3)適切な距離の保持
子ども・若者との健全な関係は、支援者としての立場を明確に保ちつつ構築することとし、個人的・親密な関係を築こうとする行為は厳に慎まれなければなりません。
7. 通報と対応手続き
子どもおよび若者への虐待、搾取、またはその他の不適切な行為が疑われる、あるいは実際に起きた場合には、速やかに通報され、適切な対応が講じられる必要があります。当法人は以下の通報・対応手続きを定め、関係者すべてに遵守を求めます。
(1)通報の義務
関係者は、子ども・若者に対するいかなる形の虐待、搾取、不適切な行為、またはそれらが疑われる状況に気づいた場合、すみやかに所定の通報先に報告しなければなりません。黙認や放置は、結果として当該行為を助長することになります。
(2)通報の窓口
当法人は、以下の通報窓口を設置し、通報者が安全に報告できる体制を整備します。通報は、対面、書面、電話、電子メールなどの手段により行うことができます。匿名による通報も受け付けますが、事実確認が困難になる場合があります。
- 通報窓口責任者:セーフガーディング担当(氏名は内部規定により指定)
- 連絡手段:公式ウェブサイト記載の専用連絡フォーム、または専用メールアドレス
(3)調査および対応
通報を受けた場合、当法人は迅速かつ公正に事実確認を行い、必要に応じて外部の専門機関と連携しながら、適切な保護措置を講じます。調査は、通報者・被害者・関係者のプライバシーを尊重し、慎重に進められます。
(4)報復の禁止
通報したことによって、通報者が不利益や報復を受けることはあってはなりません。当法人は、通報者の保護を徹底し、安全な通報環境の維持に努めます。
(5)懲戒・処分
違反が確認された場合、当法人はその行為の重大性に応じて、厳格な措置(警告、解任、契約解除、関係機関への通報等)を講じます。
8. 教育と研修
当法人は、すべての関係者が子どもおよび若者のセーフガーディングに関する十分な理解と責任ある行動を身につけられるよう、必要な教育・研修を提供します。
(1)初期研修の実施
役職員、ボランティア、インターン、パートナー機関の関係者など、本ポリシーの対象となるすべての関係者に対し、活動開始前にセーフガーディングの基本的な考え方や行動規範についての研修または説明を行います。
(2)継続的な学習機会の提供
当法人は、セーフガーディングに関する知識や対応能力を高めるため、必要に応じて定期的な学習機会(研修、ワークショップ、資料提供など)を設けます。
(3)義務としての理解と同意
関係者は、本ポリシーに明記された内容を理解した上で、書面にて同意することが求められます。同意された書面は当法人の記録として保管され、遵守義務を明確化します。
(4)内容の見直しと更新
セーフガーディングを取り巻く社会状況や、法的要請の変化に応じて、研修内容も定期的に見直され、関係者に周知されます。
9. デジタル上の対応
当法人は、インターネット、SNS、写真・映像の使用を含むすべてのオンライン環境において、子どもおよび若者の安全と尊厳を守ることを最優先に、以下の対応を徹底します。
(1)オンライン上の尊重と配慮
ウェブサイト、SNS、広報資料等において、子ども・若者の画像やストーリーを使用する場合は、事前に本人および保護責任者(保護者等)の同意を取得します。掲載内容は、本人の尊厳やプライバシーに十分に配慮した表現とし、不必要に感情を誘導する演出や誇張を避けます。
(2)個人情報の保護
子どもおよび若者の氏名(特にフルネーム)、住所、学校名、連絡先など、個人を特定し得る情報は、本人および保護責任者の同意がない限り、第三者に開示または掲載しません。
また、学校の名称が活動報告等で公表される場合であっても、特定の個人と結びつく表現は避けます。
(3)写真・映像データの取り扱い
写真・映像などの記録は、使用目的を明確にし、限定されたスタッフのみにアクセスを制限した安全な方法で管理します。
広報や報告に使用する際には、個人の特定につながるリスクがないかを確認し、必要に応じて編集やモザイク処理等を行います。
(4)支援者とのデジタル交流におけるルール
寄付者・支援者と受益者(子ども・若者)との手紙、動画、音声メッセージなどによる交流は、当法人の管理のもとで、安全な形で実施します。個人間での直接的な連絡先の交換やSNS等での個別の接触は禁止とします。
(5)不適切使用への対応
万が一、子ども・若者の画像や情報が不適切に使用された場合、当法人は直ちに当該コンテンツを削除・訂正し、被害の拡大を防ぐ措置を講じます。また、関係者への再発防止の啓発・指導も併せて行います。
(6)施設名・学校名・地域名の取り扱い
当法人は、子ども・若者の学びや暮らしの場に関する情報(例:学校名、施設名、地域名など)についても慎重に取り扱います。原則として、個人の特定につながる情報の組み合わせ(氏名+学校名など)は公表しません。
ただし、施設の代表者・運営者などから同意・要望がある場合、またその情報が既に公知である場合には、支援活動の透明性や現場理解を促進する目的で施設名や地域名を公表することがあります。その場合も、受益者個人が特定されないよう最大限の配慮を行います。
10. 報告・相談・対応の体制
当法人は、子どもおよび若者に対するあらゆる虐待や搾取、ハラスメント、その他セーフガーディングに関わる懸念・違反行為について、迅速かつ適正に対応する体制を整備しています。
(1)報告の義務とルート
すべての関係者は、子どもや若者に対する不適切な行為や、懸念される事象を知った場合、速やかに当法人が定める報告ルートに従って申告する義務を負います。報告は、本人の安全を最優先とし、匿名による通報も受け付けます。
(2)対応の原則
報告を受けた場合、当法人は被害を受けた本人の意向を尊重しつつ、迅速かつ慎重に調査・判断・対応を行います。調査にあたっては、事実確認に基づいた公平性を確保し、当事者のプライバシー保護に最大限努めます。
(3)関係機関との連携
必要に応じて、専門機関・児童福祉機関・医療機関・警察・現地の行政機関等と連携し、適切な保護と支援を講じます。
(4)記録と再発防止
報告内容と対応経過は記録として保管し、当該事案の再発防止に活かすとともに、スタッフ研修や制度改善に反映させます。
(5)報告者の保護
報告を行った者が不利益を被ることがないよう、当法人は内部告発者保護の原則に則って対応します。また、虚偽の報告や悪意ある告発があった場合には、適切な対応を行います。
11. 教育・研修・モニタリング
当法人は、関係者全員がセーフガーディングに対する理解と意識を深め、倫理的かつ適切に行動できるよう、継続的な教育・研修・モニタリングの仕組みを整備します。
(1)採用・参加時の同意取得
当法人の活動に関わるすべての関係者(職員、ボランティア、パートナーなど)は、活動開始前に本ポリシーを確認し、内容を理解した上で、遵守に関する同意書を提出するものとします。
(2)研修・説明会の実施
子どもや若者と直接的または間接的に関わる可能性のある関係者に対しては、必要に応じてセーフガーディングの基本的な考え方、対応フロー、具体的な禁止行為などを含む研修または事前説明を実施します。
(3)研修記録・更新
研修の実施記録は適切に保存し、必要に応じて定期的に内容を更新します。社会情勢や活動内容の変化に応じて、ポリシーや研修プログラムの見直しを行います。
(4)モニタリング体制
当法人は、セーフガーディングの実施状況について、定期的に内部モニタリングを行い、課題があれば早期に把握し対応します。外部の視点を取り入れる仕組みも、将来的に導入を検討します。
12. 守秘義務と内部通報の免責に関する方針
当法人は、子どもおよび若者の安全と尊厳を守るうえで、内部通報制度の信頼性および関係者のプライバシー保護を極めて重要な要素と位置づけます。
12-1. 守秘義務の徹底
通報・報告を受けた内容および通報者の情報については、通報された事実を真摯に受け止めつつ、原則として第三者に漏らすことなく、厳重に管理されるものとします。調査や対応に必要な場合を除き、当該情報は関係者以外に共有されません。
12-2. 通報者の保護と免責
子どもや若者への虐待や搾取の疑いがある行為を知り得た関係者が、適正な手順に基づいて通報を行った場合、その通報行為を理由としていかなる不利益や不当な扱いも受けることはありません。
また、善意にもとづいた通報である限り、内容が誤解や誤認に基づいていた場合でも、通報者に責任が問われることはありません。
12-3. 虚偽通報への対応
一方で、故意に事実と異なる内容を通報した場合、または悪意ある誹謗中傷を目的とした通報が認められた場合は、当法人は適切な対応措置を講じます。
13. 外部機関との連携の方針
当法人は、子どもおよび若者の保護に関して重大な懸念や被害の報告があった場合、当法人単独での対応に限界があることを認識し、必要に応じて適切な外部機関と連携します。
13-1. 関係当局との連携
通報された内容が法的または社会的に重大と判断される場合、速やかに関係当局(現地の児童福祉機関、医療機関、警察、教育機関など)に報告し、当該機関と協力して被害者の保護と回復にあたります。
現地の制度が不十分である場合にも、可能な限り信頼できる支援機関や専門家との連携を図ります。
13-2. 専門機関への相談
関係者が虐待や搾取の可能性を認識したものの、緊急性や対応の適否を判断できない場合は、当法人が信頼する外部の児童保護・人権保護等の専門機関に相談し、適切な助言を得て対応します。
13-3. 被害者の意向の尊重
外部機関との連携に際しては、被害を受けた子どもまたは若者の意思や安全への配慮を最優先とし、同意を得たうえで慎重に対応します。ただし、緊急性が高く、生命や身体への差し迫った危険があると判断される場合は、この限りではありません。
14. サポーターとの関係性に関するガイドライン
当法人は、子どもおよび若者の保護の観点から、支援者(サポーター)と受益者との関係性が信頼と尊重に基づくものであることを重要視します。支援が、いかなる形でも受益者に対する権力的・感情的な支配や依存を生じさせないよう、以下のガイドラインを設けます。
14-1. 支援者と受益者の直接交流に関する基本方針
支援者(個人・法人問わず)と受益者との直接的なやりとりは、当法人が認めた安全な形式においてのみ実施されます。個人的なSNSアカウントでの連絡や、直接的な物品の送付など、非公式な接触は禁止します。
14-2. 一方向ではなく双方向の関係性の促進
当法人は、支援する/されるという一方向の関係ではなく、互いを尊重し、学び合う関係を重視します。そのため、子どもや若者の表現の自由と自律性を尊重したかたちで交流が行われるよう努めます。
14-3. 過度な個人情報の共有防止
支援者に対して受益者の過度な個人情報(住所、家族構成、過去のトラウマなど)を提供することは避け、本人の尊厳とプライバシーが守られるよう配慮します。
14-4. 支援者の立場の明確化
支援者はあくまで当法人の活動趣旨に賛同するパートナーであり、受益者に対して指示・助言・管理などの立場にはないことを明確にします。
15. 支援者との交流に関するガイドライン
当法人は、支援者と受益者のあいだに尊重と信頼に基づく健全な関係を築くことを目指しています。その一環として、交流手段を設ける場合には、以下の指針に基づき、受益者の安全と尊厳を最優先に運用します。
15-1. 交流手段の位置づけ
手紙・写真・動画などによる間接的な交流は、受益者の表現機会のひとつであり、また支援者が活動の意義を実感する重要なきっかけともなります。ただし、その交流は決して「見返り」として提供されるものではなく、受益者の意思と尊厳を尊重した上で慎重に運用されます。
15-2. 交流における同意と意思の尊重
交流を行う際には、必ず受益者本人および、その保護責任者(保護者など)から事前の同意を得ます。また、受益者の年齢や理解度に応じて、内容や形式について十分に説明したうえで意思確認を行います。交流への参加はあくまで任意であり、強制されるものではありません。
15-3. 受益者のプライバシー保護
受益者の個人情報(詳細な住所・電話番号・個人を特定できる連絡先など)は、支援者に直接共有されることはありません。
ただし、交流の内容(映像・手紙・写真)に含まれる背景や語りの中で、学校の制服や家庭の状況に関する情報が間接的に伝わる場合があります。これらについては、事前に本人および、その保護責任者(保護者など)の同意を得たうえで、支援者との関係性や本人の尊厳を損なわないよう慎重に取り扱います。
15-4. 支援者への対応
支援者からの返信や反応に関しては、受益者に過度な期待をかけることがないよう、適切なフィルターを通じて管理されます。支援者からのメッセージに含まれる不適切な表現やプライバシーに関わる内容については、当法人が事前確認を行い、必要に応じて対応を行います。
16. 情報の共有制限
当法人は、子どもおよび若者のプライバシーと安全を守るため、個人情報の取り扱いに十分な配慮を行います。以下の各項目に関して、本人および必要に応じて保護責任者(保護者等)の明確な同意がない限り、第三者への開示・掲載・共有は行いません。
16-1. 個人を特定しうる情報の管理
氏名、住所、連絡先、顔写真、学校名、所属施設名、家族構成、健康状態など、本人を特定しうる情報は、適切な保護措置のもとで管理され、不要不急に公開・共有されることはありません。
16-2. 地域名・学校名等の開示基準
支援対象の地域名(例:ナイロビ市キベラ地区など)は、対象者の識別性が低く、文脈上必要と判断される場合に限り、公開することがあります。ただし、特定の学校名・施設名などが併記されることで個人が推測可能になる場合には、公開を控えるか、事前に関係者の明確な同意を得るものとします。
16-3. 協働先による情報開示との整合性
受益者が所属する学校・施設の運営者や協働団体が、組織としての判断で校名や所属情報を公開する場合であっても、当法人は独自にリスクを評価し、個人情報保護の観点から慎重に対応します。
16-4. 画像・映像・エピソードの取り扱い
広報や報告書等に使用する画像・映像・ストーリーは、本人および保護責任者の同意を得た上で、尊厳を損なわない範囲で使用します。多数の人物が写っている写真等についても、必要に応じて匿名化・ぼかし処理等を行い、個人の特定を防ぐよう配慮します。
17. 人材採用・研修・契約時の同意に関する取り組み
17-1. 採用・契約時の同意
当法人は、関係者(職員・業務委託・ボランティア・インターン等)を採用または契約する際、本ポリシーを提示し、その内容を理解・同意したことを文書により確認します。署名された同意書は、必要に応じて更新され、当法人において適切に保管されます。
17-2. 研修の実施
当法人は、子どもおよび若者と接する可能性のある関係者に対し、セーフガーディングに関する基本的な考え方、禁止事項、適切な対応方法についての研修または事前説明を行います。研修は、活動内容や対象者の特性に応じて柔軟に設計され、必要に応じて更新されます。
17-3. 適性確認と留意事項
採用・契約にあたっては、関係者に対して、過去において子どもや若者への虐待・暴力・搾取などに関与した事実がないことを自己申告で確認し、不適切な行動歴がないことに同意を求めます。とくに、受益者と継続的に関わる職務に就く場合には、セーフガーディングの重要性についての理解と、基本的な人権意識・配慮が求められる旨を明確に伝えます。
18. 本ポリシーの周知・更新
18-1. 周知の徹底
当法人は、すべての関係者が本ポリシーの趣旨と内容を理解し、日常的な業務や活動の中で実践できるよう、継続的な周知に努めます。新たに関与する者に対しては、関与開始前に本ポリシーを提示し、理解と同意を得ることを原則とします。
18-2. 定期的な見直し
本ポリシーは、社会状況、法制度、活動地の環境の変化、当法人の活動内容の変化等を踏まえ、定期的に見直しを行います。必要に応じて改訂を行い、最新版を当法人の公式ウェブサイト等にて公表します。
18-3. 改訂時の対応
本ポリシーの内容が変更された場合には、速やかに関係者に通知し、改訂後の内容に基づいた同意の取得や研修等を実施します。改訂版の発効日以降も活動を継続する場合は、新たな内容に同意したものとみなします。
19. 問い合わせ窓口
本ポリシーに関するご質問、ご意見、通報、または懸念事項がある場合は、以下の窓口までご連絡ください。ご連絡内容は適切に管理され、必要に応じて迅速かつ誠実に対応いたします。
NPO法人シフトエイティ(SHIFT80)
所在地:〒135-0042 東京都江東区木場3-18-17
お問い合わせフォームはこちら
ウェブサイト:https://shift80.org
※通報・相談内容の秘密は厳守され、通報したことによる不利益な扱いは一切ありません。